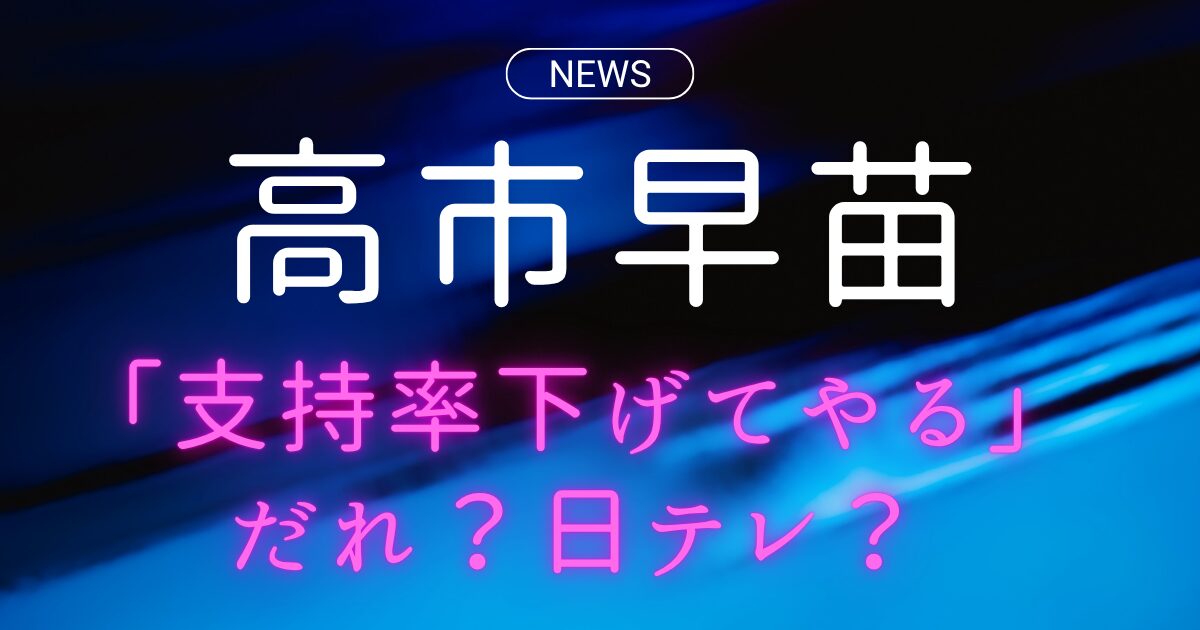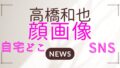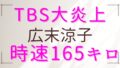囲み取材中に漏れた「支持率下げてやる」という発言が、高市早苗氏を巡る大きな波紋を呼んでいます。放送されたのは日本テレビの生中継。意図的とも受け取れる内容と、のちに問題部分が削除された編集対応に、「隠蔽では?」との声がSNSで広がりました。では、実際に発言したのは誰なのか?本当に日テレ関係者ではないのか?
この記事では、事件の詳細から映像に映った内容、音声の特徴、発言者の正体をめぐる分析、日テレの対応、そして世論の反応までを丁寧に整理。読者が気になる真相と報道の在り方を徹底的に追います。
1. 発言事件の全貌
メディアが世論誘導して引っかかる時代は終わったという自覚もなく、オールドメディアに世間から厳しい目が向けられている認識もない。
プロとしてメディアで働く人間なら冗談でも言ってはいけない https://t.co/maBhpLxNWG— Mi2 (@mi2_yes) October 8, 2025
出典:X Mi2(@mi2_yes)
1-1. 放送事故が起きた背景と日時
2025年10月7日、自民党新総裁に選ばれた高市早苗氏が公明党関係者との会談後、報道陣による囲み取材に応じた際の出来事でした。この様子は日本テレビにより生中継されており、全国でリアルタイムに視聴されていました。
取材は高市氏が登場する前から始まっており、その時点で現場には複数の報道関係者が待機していたと見られます。ところが、その生中継映像の中で、報道関係者のものと推測される声がマイクに拾われ、不適切な発言が全国に放送されるという“放送事故”が発生したのです。
発言内容は非常に挑発的で、「支持率下げてやる」「支持率が下がるような写真しか出さねーぞ」といった政治的意図をにおわせるものでした。政権の公平な報道を担うべき現場で飛び出したこの発言に、多くの視聴者が強い違和感と怒りを覚える結果となりました。
しかも問題の音声は明瞭に収録されており、誰かが偶然に発した私語とは到底思えない内容であったため、その背景や意図に注目が集まりました。生中継中の出来事だっただけに、隠すことも編集することもできず、そのまま視聴者の耳に届いてしまったのです。
このようにして「放送事故」とも言える今回の事件は、ただのマイクトラブルでは片付けられない、政治とメディアの関係性や報道姿勢を問う深刻な問題として、瞬く間に国民の注目を集めることになりました。
1-2. 問題の発言内容と発言者の状況
注目された発言は2つあり、「支持率下げてやる」「支持率が下がるような写真しか出さねーぞ」という具体的な言葉が、マイク越しにはっきりと拾われていました。発言者は映像には映っておらず、音声のみが記録されている形です。
音声からは、発言者が男性であることが推測されており、年齢はおおよそ40〜50代とみられています。話し方は標準語であり、報道現場に慣れている記者やカメラマンのような語調であることから、メディア関係者である可能性が高いとされています。
また、発言者がマイクの近くにいたと見られる点からも、取材エリアの中でも比較的中心にいた人物、つまり主要メディアの関係者であった可能性があるという指摘も出ています。一部では、記者ではなくフリーカメラマンの可能性や、他局の人間ではないかとの見方も浮上しており、発言者の特定は現在も困難を極めています。
日テレ側は「当社関係者ではない」と公式に表明していますが、それでも国民の間には「本当にそうなのか?」という疑念が残り続けています。特に、公正中立を求められる報道の場でこのような発言が飛び出したことに対し、発言者が誰であるかの追及が強く求められています。
2. その時、映像で何が流れたのか?
【悲報】高市早苗新総裁の会見前に高市さんを馬鹿にしまくる記者
「麻生さんからイヤフォンで指示聞いたりして(笑)」
これどこの記者でしょうか?
必ず特定して会見から締め出すべき pic.twitter.com/4FWvH4d18X— あーぁ (@sxzBST) October 7, 2025
2-1. 「支持率下げてやる」の音声が入った瞬間
この問題の発言が流れたのは、生中継が続いていた囲み取材の準備中でした。高市早苗氏がまだ登場していない段階で、報道関係者と思われる人物の私語がそのまま放送に乗ってしまったのです。
しかもその発言は、一瞬の雑音や聞き間違いではなく、はっきりと聞き取れるレベルでマイクに拾われていました。視聴していた多くの人が「今、何かおかしなことを言わなかったか?」と気付き、巻き戻して確認するなどして発言の内容が次第に明らかになりました。
映像内では発言者の姿は確認されておらず、カメラは囲み取材エリアを映していたものの、音声だけが突如差し込まれた形です。マイクが集音していたことから、発言はかなり近い距離で発せられたと推測されています。
この瞬間、ただの雑談では済まされない内容が全国放送で流れたことで、「公平な報道」を求める立場としてのメディアに対する信頼は、大きく揺らぐこととなりました。
2-2. SNSで瞬時に拡散された怒りと疑問
放送直後から、X(旧Twitter)を中心に視聴者の反応が爆発的に広がりました。「今の発言、聞こえた?」「記者が支持率下げるって言ってたけど、本気なの?」「完全に印象操作では?」といったコメントが続出し、関連ワードが一気にトレンド入りしました。
「#支持率下げてやる」「#日テレ隠蔽」などのハッシュタグも次々に登場し、情報は瞬く間に拡散され、ネットユーザーの怒りが噴き上がる状況となりました。特に注目されたのは、「報道関係者が中立でない発言をしている」「政治家に対する恣意的なバイアスがかかっている」という点です。
さらに、映像の該当部分がその後に削除されていたことで、「隠蔽ではないか」「証拠隠滅のように見える」といった疑念が生じ、火に油を注ぐ形になりました。
SNSでは「これはもう報道テロ」「政治報道の信頼が崩れる」といった声まで出ており、単なる放送事故以上の、社会的な問題として発展しています。中でも、高市早苗氏に対する同情の声や、女性政治家へのメディア対応に対する批判も目立ち始め、単一の事件が報道全体への信頼に関わる議論へと広がっているのが現状です。
3. 「誰が言ったのか?」記者の正体を追う
3-1. 音声の特徴(年齢・性別・話し方)からの推定
問題の音声は、2025年10月7日の囲み取材の生中継中に流れたもので、「支持率下げてやる」「支持率が下がるような写真しか出さねーぞ」と、かなり明確に聞き取れる内容でした。発言した人物は画面に映っておらず、声だけが拾われていますが、音質や話し方からいくつかの特徴が推測されています。
まず、声の主は明らかに男性で、年齢層は40〜50代と思われます。声質は比較的落ち着いており、いわゆる業務的な口調に近い印象を与えます。方言などの特徴はなく、標準語を使っていたことから、全国メディア関係者の可能性が高いと見る向きもあります。
また、音声の拾われ方から、発言者は取材現場に設置されたマイクのかなり近くにいたと推測されており、会見の取材に実際に関与していた人物である可能性が極めて高いです。会場の騒音の中でもしっかりと拾われていることから、マイクから1〜2メートル以内にいた可能性も考えられます。
言葉遣いにも注目すべき点があります。「写真しか出さねーぞ」という口調は、フランクでやや粗い印象を受けるため、記者というよりも撮影を担当するカメラマンのような人物の発言であった可能性も否定できません。
3-2. 他局記者説・フリーカメラマン説・通行人説の検証
この発言が誰によるものなのかについて、インターネット上ではさまざまな憶測が飛び交っています。まず疑われたのは、映像を放送していた日本テレビの社員や記者でしたが、後述の通り、日本テレビ側は関与を否定しています。
そこで次に挙げられたのが「他局記者説」です。取材現場には通常、複数のメディアが合同で入り、どの局の記者がどこにいたのかは正確に把握しづらい状況です。発言の内容からは、何らかの意図をもって政治家のイメージを操作しようとする意識が感じられ、それが記者のものだった場合には非常に深刻な問題になります。
一方で「フリーカメラマン説」も根強くあります。映像のトーンや発言のざっくばらんな口調から、報道記者というよりも、現場で撮影を担当する立場の人物が不用意に発言した可能性も考えられています。フリーカメラマンの場合、所属組織が明確でないため、責任の所在が曖昧になることも少なくありません。
一部には「通行人説」もありますが、会見の場は報道関係者以外の立ち入りが制限されている場合が多いため、通行人がマイクに拾われるような位置にいた可能性は極めて低いと考えられています。現実的には、報道関係者の中の誰かの発言だったとみるのが自然です。
3-3. 現場の構成(各社混在の可能性)と特定の難しさ
囲み取材の現場では、複数のメディアが混在して取材にあたるのが一般的です。テレビ局だけでなく、新聞社、通信社、さらにはフリーの記者やカメラマンなど、様々な立場のメディア関係者が同じ空間にひしめき合って情報を取りに行く構造となっています。
そのため、誰がどの位置にいたかを後から正確に特定するのは非常に難しいのが現実です。特に映像に映っていない人物の発言である以上、映像や音声だけでは身元の特定には限界があります。
また、現場には報道関係者以外にも技術スタッフや協力会社の関係者がいた可能性もあり、さらに人物の特定を複雑にしています。現時点で明確な証拠がなく、発言者の音声分析にも限界がある中で、「誰が発言したのか?」という問いに対する答えは出ていない状況です。
とはいえ、「報道の現場でこのような発言がされた」という事実だけでも、視聴者や国民の信頼を大きく損なうことになりかねません。だからこそ、各メディアや関係団体による徹底的な調査と、事実関係の公開が強く求められています。
4. 日テレの対応と「隠蔽」疑惑
4-1. 問題部分の削除と編集理由の説明
今回の発言が大きな波紋を呼んだ理由のひとつが、当初配信された生中継映像から、後にアップロードされた見逃し配信版で問題の音声部分が削除されていたという点です。この編集対応が「隠蔽ではないか」との批判を招く結果となりました。
これに対して日本テレビは、「通常行っている編集作業の一環」と説明しました。生中継では本番前の様子も含めて配信されることがありますが、それらは本来放送を想定していない部分であり、見逃し配信用に編集する際にはカットされるのが一般的だというのが日テレの立場です。
しかしながら、この編集がちょうど問題の発言を含む部分だったことが、視聴者の疑念を招く結果となり、「都合の悪い部分を消したのではないか」との声が噴出しました。編集理由が形式的であるほど、逆に「隠したい意図があったのでは」との印象が強まり、結果として信頼の低下を招いてしまっています。
4-2. 「弊社関係者ではない」とする日テレの公式コメント
日本テレビの総務局広報部は、取材に対して「当社関係者による発言ではない」と明確に否定しています。さらに、「現場で収録されていた音声は、他社の関係者のものと推定される」との見解も示されました。
このコメントは、放送局としての立場を示すうえでは必要な対応ですが、視聴者の疑念を完全に払拭するには至っていません。「では誰の発言だったのか?」「なぜもっと積極的に調査しないのか?」という不満の声は依然として根強く、納得できないと感じる人も少なくありません。
特に、発言が明確な敵意をもって政治家を貶める内容であったことから、「仮に他社の記者だったとしても、全社で調査にあたるべきではないか」という意見も多く出ています。問題の根本は「誰が言ったか」だけでなく、「報道機関の在り方そのもの」へと波及しているのです。
4-3. 編集対応への視聴者・専門家の批判と憶測
一連の対応に対し、SNS上では「日テレは信頼できない」「説明責任を果たしていない」といった批判が噴出しています。また、メディア倫理の観点からも、報道関係者が意図的に政治家の印象を操作しようとした可能性がある点について、専門家からの指摘も出始めています。
さらに、編集部分の削除については、「事実上の証拠隠滅だ」「削除されたことで逆に問題の重さが際立った」という評価もあり、テレビ局の対応がむしろ事態を悪化させたとの見方も少なくありません。
視聴者の信頼を取り戻すためには、各社が連携し、現場の音声ログや関係者の証言をもとに、事実関係を徹底的に調査し、公表する姿勢が求められています。現在のままでは、「報道が信用できない」という風潮がさらに広がりかねず、日本のジャーナリズム全体への信頼問題に発展していく可能性さえあります。
5. 世論の反応と「高市早苗がかわいそう」という声
5-1. SNSで広がった擁護と批判の声
「支持率下げてやる」という発言が中継中に流れた直後から、SNSは大きな騒ぎとなりました。特にX(旧Twitter)では、「#支持率下げてやる」「#日テレ隠蔽」などのハッシュタグがトレンド入りし、瞬時に全国的な話題となりました。多くのユーザーが驚きと怒りを表明し、拡散が止まらない状態に。
視聴者の声は大きく二つに分かれました。一方では、「高市さんが気の毒すぎる」「こんなやり方で印象操作をするのは許されない」と、高市早苗氏に対する同情とメディアへの怒りの声が多数上がりました。彼女が登場する前の発言だったこともあり、本人が何もしていない段階で攻撃されているように感じた人が多かったようです。
もう一方では、「これが記者の本音なのか?」「どこのメディアか、徹底的に調べて公表すべきだ」と、発言者の特定と責任追及を求める声が急増。政治家への個人的な意図が混じった報道姿勢に対して、強い疑問を持つ国民が増えていきました。
5-2. 女性政治家への偏見と報道のバイアス問題
今回の騒動では、「女性政治家」に対するメディアの扱いについても再び注目が集まっています。高市早苗氏は、自民党初の女性総裁という立場にあり、就任直後という節目のタイミングでこのような発言が飛び出したことから、「女性であることに対する偏見があったのではないか」という声も見られました。
特に、「笑顔で会見に応じている裏で、そんな発言をされていたなんて」といった感情的な反応が広がり、女性である高市氏が標的にされやすい環境に置かれていたのではないかという指摘も出ています。
報道の中立性が求められるなか、女性政治家に対して過剰な印象操作が行われた可能性があるとすれば、それは単なる一記者の問題にとどまらず、メディア全体の構造的な問題とも言えるでしょう。
5-3. 公正な報道姿勢に対する国民の不信感
この騒動をきっかけに、「メディアは本当に中立なのか?」という根本的な疑問を持つ人が増えました。報道関係者が公平性を欠く発言をすること自体が信じがたい事態であり、その音声が公共の電波を通じて全国に流れたという事実は、メディアの信頼を根底から揺るがすものでした。
多くの視聴者が、「もうテレビ報道は信用できない」「自分たちで情報を見極める必要がある」といった声を上げています。中でも政治報道に対する懐疑的な視線は一段と強まり、テレビ・新聞といった従来の報道媒体が担っていた「信頼の拠り所」としての役割が大きく揺らいでいるように感じられます。
今後、こうした不信感を払拭するためには、メディア側が透明性の高い対応を取り、報道に対する説明責任を果たしていくことが不可欠です。
6. 報道倫理と今後の調査の行方
6-1. 報道の“第四の権力”としての責任
報道機関は、司法・立法・行政に次ぐ「第四の権力」として、国民の知る権利を支える非常に重要な役割を担っています。そのため、政治に対しては特に中立かつ公平であることが求められます。
今回のように「支持率を下げる」といった発言が報道関係者から出たとすれば、もはやジャーナリズムの基本精神を揺るがす事件です。情報を届ける立場の人間が、その内容に恣意的な意図を加えてしまえば、それは“報道”ではなく“操作”になってしまいます。
この問題は単なる一記者の不適切な発言では済まされず、報道業界全体が今一度、自らの職業倫理を見つめ直す契機とすべきです。
6-2. 民放連や各局による調査の可能性
現在のところ、問題発言に対して明確な調査結果は発表されていません。しかし、視聴者の間では「真相を公表してほしい」「どこの誰が発言したのか明確にしてほしい」といった声が日々高まっています。
特に、民放連(日本民間放送連盟)や各テレビ局、新聞社などの報道機関には、業界全体でこの問題に向き合う姿勢が求められています。個々の放送局の責任だけにせず、報道機関全体の透明性と信頼回復のためにも、横断的な調査が行われることが期待されています。
仮に発言者が特定されなかったとしても、「このような事態を二度と起こさないために何をするか」を明示することで、視聴者に対する誠意を示すことは可能です。
6-3. この騒動が報道界に残す教訓
今回の発言騒動は、今後の報道界に多くの課題と教訓を残しました。一つは、記者やカメラマンを含めたすべての報道関係者に対する教育と研修の必要性です。現場では何気ない一言が全国放送に乗る可能性があり、それが信頼を傷つける結果にもなりかねないという緊張感を持ち続ける必要があります。
また、報道機関が自らの過ちをどう認め、どう修正し、どう公表していくのかという姿勢も問われています。隠蔽や責任のなすりつけ合いではなく、真摯に視聴者と向き合う姿勢こそが、失われた信頼を取り戻す第一歩です。
7. まとめ|支持率を「下げてやる」は誰の声だったのか?

7-1. 今も続く「犯人探し」と信頼回復の鍵
問題の発言から時間が経過しても、未だに「誰が言ったのか」という核心部分は明らかになっていません。関係各所の調査や報道も止まりがちになり、「うやむやにされるのでは?」という不安の声もあります。
一方で、こうした問題を放置することは、報道全体への不信感をさらに深める結果となりかねません。今こそ、どのメディアも忖度なしで事実を追及し、関係者への聞き取りや音声解析など、できる限りの努力を尽くすべき局面にあります。
何よりも重要なのは、視聴者の目線に立ち、誠実に説明し、透明性をもって行動することです。それが、報道機関が失った信頼を少しずつでも取り戻していく唯一の道です。
7-2. 読者・視聴者が今できること
この騒動を通じて私たち視聴者ができることは、報道をただ受け取るのではなく、常に「その情報は誰が、どんな意図で伝えているのか?」と考える習慣を持つことです。一つのメディアや一つの報道だけに頼るのではなく、複数の情報源を照らし合わせ、自分の判断軸を持つことが求められています。
また、メディアに対して声を届けることも有効です。SNSでの意見表明や、放送局への問い合わせなど、個人が意見を伝える手段はたくさんあります。報道が真に公正であってほしいと願うなら、視聴者自身が「おかしい」と思った時に、黙らず声を上げることが、メディアを健全に保つ力となるのです。
おすすめ記事
松本光生の顔画像・SNS・自宅はどこ?被害者の会社名は?最新情報!