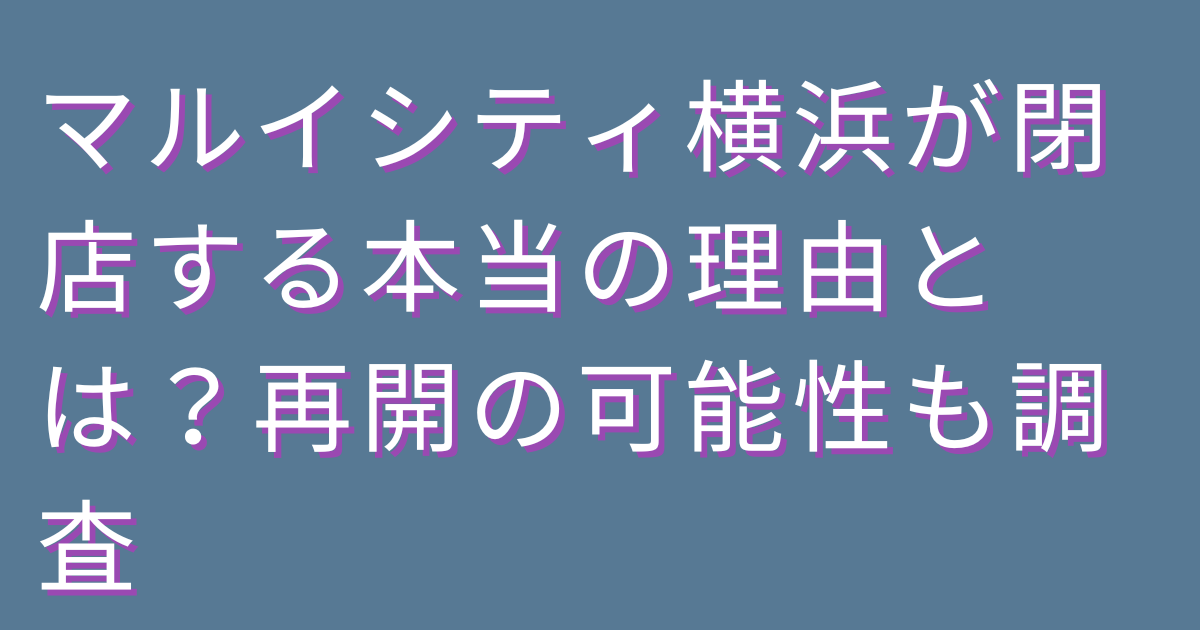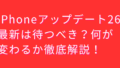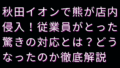2026年2月末、長年横浜駅東口で親しまれてきた「マルイシティ横浜」が閉店します。1996年の開業以来、若者やファミリー層のショッピングスポットとしてにぎわってきた施設が、なぜその幕を下ろすのか――。時代とともに変化する消費スタイル、ECの台頭、ホビー路線への転換など、その背景にはさまざまな事情が絡んでいます。
この記事では、閉店の理由や施設の歩み、売上やテナントの変遷、さらに跡地の今後や再開の可能性についても詳しく解説します。
1. なぜマルイシティ横浜は閉店するのか?
1-1. 29年の歴史に幕…2026年2月末で営業終了の理由とは
マルイシティ横浜は、1996年に横浜駅東口のスカイビル内に開業して以来、約29年間にわたり地域に根差した商業施設として親しまれてきました。そんな歴史ある施設が2026年2月末をもって閉店することが明らかになり、多くの利用者に衝撃を与えています。
閉店の背景には、商業施設としての収益性の低下が深く関わっています。近年の消費スタイルの変化や競争環境の激化により、売上は右肩下がりの状況が続いていました。とくに最盛期とされる1998年度の売上255億円から、2024年度には約124億円へと半減。構造的な収益悪化が決断の一因となりました。
加えて、施設全体の老朽化や入居ビルの再編など、経営判断としての転換点を迎えていたことも大きな理由とされています。
1-2. EC(電子商取引)拡大と「モノ消費」から「コト消費」への転換
かつては若年層向けのアパレルを中心に支持を集めたマルイシティ横浜ですが、近年はネットショッピングの台頭によって来店客数に影響が出ていました。特に10〜30代を中心に、洋服や雑貨を「店舗で買う」文化が希薄になり、ECサイトでの購入が主流に。
このような「モノ消費」の低迷に加え、旅行やイベント、アニメやゲーム体験など「コト消費」への関心が強まる中で、店舗のテナント構成も柔軟な変化を求められていました。
しかし、施設としての対応には限界があり、時代の変化に即応するには大規模なリニューアルが不可欠だったことが推察されます。
1-3. ホビー系への転換でも業績回復できなかった背景
マルイ側もこうした時代の流れに対応すべく、2010年代以降、売り場構成をホビーやエンタメ系にシフトさせました。たとえば2018年には人気ゲーム「ポケットモンスター」の公式ショップ「ポケモンセンターヨコハマ」を、横浜みなとみらいから誘致。翌2019年には中古品を扱う「駿河屋」も加わり、オタク文化や家族連れ向けの施設としての色合いを強めました。
一見すると戦略的なリブランディングに見えますが、結果として業績の大幅な改善にはつながりませんでした。理由の一つは、ホビー系に特化した競合施設の増加や、すでにオンライン化されたファンマーケットの存在です。
「訪れる理由」が少ないと感じる消費者にとって、リアル店舗への集客はやはり難しい課題であったといえるでしょう。
2. 閉店までの営業状況と現在の売り場構成
2-1. 売上推移:最盛期の255億円から半減した現在
マルイシティ横浜の売上は、最盛期の1998年度において255億円を記録していました。これは当時の横浜駅東口エリアにおける中心的な商業施設であったことを示しています。
しかしながら、EC市場の拡大やライフスタイルの変化により、来店者数の減少が続き、2024年度の売上は約124億円と、最盛期の約半分に落ち込んでいます。
店舗規模や立地を考慮すれば決して小さな売上ではないものの、マルイグループが掲げる経営効率や再投資の観点から見れば、施設としての役割に限界が見えていたとも言えます。
2-2. テナント構成の変遷:ポケモンセンターや駿河屋の誘致
近年のテナント構成を見ると、アパレル中心からホビーやゲーム関連へと明らかな変化が見られます。
特に2018年に移転オープンした「ポケモンセンターヨコハマ」は、ファミリー層や外国人観光客を中心に話題となり、多くの来場者を呼び込みました。また、中古ホビー販売の「駿河屋」も人気の一翼を担っていました。
しかし、それ以外のフロアでは目新しさや独自性に欠ける印象も否めず、館全体としてのブランド力や統一感を保つのが難しかったと見られます。
2-3. 年間来場者900万人規模だった施設の今
マルイシティ横浜は、年間で約900万人もの来場者を誇っていた時期がありました。これは横浜駅周辺でも中堅クラスの商業施設として確かな存在感を示していたことを物語っています。
しかし、テナントの入れ替わりや施設の老朽化、他の新興施設との競争激化によって、かつてのにぎわいは徐々に薄れていきました。
「昔はよく行っていたけれど、最近はあまり行かなくなった」という声も多く、地元利用者の足が遠のいていったことが、施設閉店の引き金となった可能性は高いでしょう。
3. 今後の再開・リニューアルの可能性は?
3-1. 「マルイ」ブランドとしての再出発はあるのか
マルイシティ横浜の閉店後、同じ「マルイ」ブランドとして横浜エリアで再出発する可能性については、現時点で具体的な計画は公表されていません。
ただし、他エリアではマルイが「モディ」や「マルイファミリー」として業態転換を行いながら再展開している例もあり、完全撤退というよりは「形を変えた出店」という道も考えられます。
横浜のような大都市圏におけるブランド再構築は、企業戦略として十分な選択肢となるでしょう。
3-2. ファミリー向け施設「モディ」への転換例から予測
実際にマルイグループでは、ファミリー層をターゲットにした「モディ」業態への転換を他の地域で進めています。たとえば小田急沿線の町田では、従来の「マルイ」から「町田モディ」へと業態を変更し、生活雑貨や飲食、教育系テナントを中心に構成することで一定の集客を実現しています。
横浜駅周辺は再開発が進むエリアでもあるため、類似の業態での再登場があっても不思議ではありません。
再開に向けては、地域ニーズや商圏分析に基づく形での再投資判断が求められるでしょう。
3-3. 跡地はどうなる?後継テナントや再開発の可能性
マルイシティ横浜が入居しているスカイビルは、地上29階建ての高層ビルで、利便性の高い立地にあります。今後はその立地を活かし、別業態のテナントが入る可能性も高いと見られています。
特に、飲食・オフィス複合型施設や、体験型エンタメ施設など、トレンドを反映した再開発が期待されるエリアでもあるため、全面的な再設計が行われる可能性もあります。
一方で、商業施設の空きフロア問題が全国的に広がる中で、単純な代替テナントの誘致だけではなく、再開発全体の方向性が問われる局面にあるのも事実です。今後の動きに注目が集まります。
4. マルイシティ横浜とはどんな場所だったのか?
4-1. 1996年開業からの歩みと周辺環境との関係性
マルイシティ横浜は1996年、横浜駅東口エリアの再開発とともに誕生しました。横浜駅周辺は、西口に比べて長らく商業施設が限定されていたエリアでしたが、この年にスカイビルが建て替えられたのを機に、都市機能の拡充が進みました。
マルイシティ横浜は、若手ビジネスパーソンやOL層をターゲットとしたアパレルや雑貨を中心に展開し、「洗練された都会のライフスタイル」を提供する拠点として定着。当時の横浜市民にとっては、ファッションの最先端を感じられる場としての印象が強く、「週末はマルイで過ごす」というライフスタイルが定番だった方も少なくありません。
また、東口側の開発が進んだことで、横浜ベイクォーターやそごう横浜店、ポルタ地下街との連携も強まり、エリア全体としての回遊性が高まったのもこの時期です。
4-2. 横浜駅東口・スカイビルとの結びつき
マルイシティ横浜が入っているスカイビルは、地上29階・地下3階の大型複合ビルであり、ホテルやクリニック、飲食店などさまざまなテナントが入居しています。マルイはその中心商業区画を担う存在として、地下1階から地上8階まで約1万6500㎡の売り場を構えていました。
この立地は、JR横浜駅からデッキで直結しており、利便性が非常に高いことから、雨の日でも気軽に立ち寄れる「駅チカ百貨店」として親しまれてきました。スカイビルとマルイの存在は一体的に認識されており、特に若年層や通勤途中のビジネスパーソンにとっては生活導線の一部になっていました。
しかし、近年はその商業的価値に陰りが見え始め、駅周辺の他施設との競争激化や、ビル自体の老朽化なども影響し、再編が必要とされる時期を迎えていたのです。
4-3. 地元ユーザーやファンの声
マルイシティ横浜の閉店が報じられてから、SNSや地域掲示板などでは「青春の思い出の場所がなくなるのは寂しい」「学生時代に初めて買い物デートした場所だった」といった声が多く見受けられます。
中には「ポケモンセンターがあった頃は子どもと一緒に通っていた」「駿河屋で推しグッズを探すのが楽しかった」といった、ホビー系テナントのファン層からの投稿もあり、幅広い年代から支持されていたことがうかがえます。
長年、横浜の“日常の中にある非日常”を提供し続けてきた存在として、多くの地元ユーザーにとって思い出が詰まった施設だったのは間違いありません。
5. マルイシティ横浜閉店が横浜の商業地に与える影響
5-1. 周辺施設(そごう・高島屋・ジョイナスなど)との比較
横浜駅周辺には、大型百貨店や商業施設が数多くひしめいています。西口には「横浜高島屋」「ジョイナス」、東口には「そごう横浜店」や「横浜ベイクォーター」が立地し、それぞれ異なるターゲット層に向けてサービスを提供しています。
マルイシティ横浜はこれらの中で中堅的な位置づけにあり、特に若年層やホビー愛好者をメインターゲットとしていました。そのため、今回の閉店によって、同様の趣味系・サブカルチャー系ニーズの受け皿が一時的に減少する可能性があります。
また、競合施設側としては、この隙間を埋める形での新たなテナント誘致や業態転換が進むことが予想され、今後の横浜駅周辺の商業バランスにも一定の影響を与えると考えられます。
5-2. 競争激化と業態転換ラッシュの実態
近年の横浜駅周辺では、従来の百貨店型ビジネスが限界を迎える中で、各施設が「エンタメ性」「体験型」あるいは「飲食・サービス系」へと大きく舵を切る流れが加速しています。
たとえば、そごう横浜店では高級ブランドや化粧品に重点を置いた売場改革が進められ、高島屋も食料品や婦人雑貨などの分野を強化する動きが見られます。一方、ポルタやジョイナスでは若年層向けファッションやグルメの拡充が進んでおり、「何を体験しに行くか」という明確な目的がある施設が選ばれる傾向にあります。
マルイシティ横浜もホビー系にシフトして対応を試みましたが、時代のニーズを先回りするにはやや時間が足りなかったという印象です。
5-3. 横浜駅周辺の再編成が進む理由
横浜駅は、日本国内でも屈指のターミナル駅として、多くの路線が交差する巨大な交通拠点です。それゆえに駅周辺は常に商業開発が進められ、今も再開発や建て替えが次々と実施されています。
マルイシティ横浜の閉店も、単なる収益悪化というだけでなく、こうした都市再編の流れの中に組み込まれているとも考えられます。スカイビル自体の再利用や、より多機能な複合施設への転換など、長期的な都市計画に基づく動きである可能性もあるでしょう。
今後の横浜駅周辺は、「駅に行けばすべてがそろう」だけでなく、「駅に行けば新しい体験ができる」場所としての進化が求められています。そのためには、時代に即した商業戦略と再開発の融合が不可欠となっていくはずです。
※本記事は公開情報をもとに作成しておりますが、内容には誤りや古い情報が含まれている可能性があります。正確な情報は公式発表や信頼できる報道機関の情報をご確認ください。
おすすめ記事
iPhoneアップデート26最新は待つべき?何が変わるか徹底解説!
33歳で福島市長に当選!馬場雄基は何者?経歴・学歴・結婚を解説