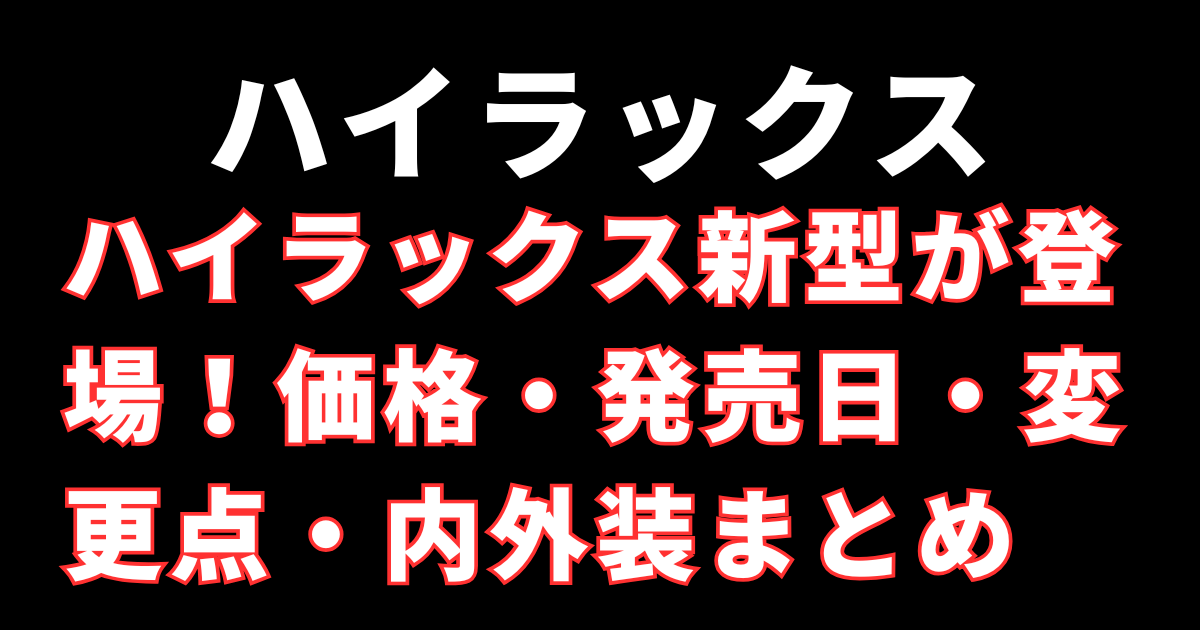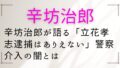近年、アウトドア需要の高まりや災害時の対応力から、ピックアップトラックへの注目が再び集まっています。中でも「新型ハイラックス」は、日本発売の時期や価格、どこがどう変わったのかといった情報を求める声が増えているのが現状です。
この記事では、ハイラックスの第9世代モデルとしての進化ポイントや、ディーゼル・EV・FCEVという多様なパワートレーン展開、日本での発売予定時期、気になる価格帯、そして内装の変化までを総合的に解説します。
新型ハイラックスが「どんな人に向いているのか」も含めて、購入検討中の方に役立つ情報を分かりやすくまとめました。この記事を読むことで、新型ハイラックスの全体像がしっかり掴めます。
1. 新型ハイラックスとは?

出典:TOYOTA
1-1. 第9世代へ進化!60年の歴史を継ぐ最新モデル
トヨタのピックアップトラック「ハイラックス」は、1968年に初代モデルが誕生して以来、世界中で長く愛されてきたロングセラーモデルです。2025年現在で、その歴史は60年以上にも及びます。
今回発表された新型ハイラックスは、ついに第9世代へと突入。これまでのユーザーからのフィードバックや、過酷な環境での実績をもとに、さらに耐久性と走行性能を高めた進化型となっています。
特に注目すべきは、「マルチパスウェイ戦略」と呼ばれるトヨタの方針に基づき、様々なパワートレーンを展開している点です。ディーゼル、電気自動車(EV)、さらには燃料電池車(FCEV)にまで対応する構造になっており、世界の多様なニーズに応えるグローバルな姿勢がうかがえます。
環境性能にも配慮しながら、過酷なオフロードにも耐えうる信頼性を併せ持つモデルとして、まさに「これからの時代のピックアップ」と言えるでしょう。
1-2. 初公開はタイ・バンコク!なぜタイなのか?
新型ハイラックスのワールドプレミアは、2025年11月、タイ・バンコクで実施されました。なぜタイでの発表だったのか疑問に感じた方も多いかもしれませんが、それには深い理由があります。
ハイラックスは、タイでは“国民車”とも言われるほど高い人気を誇り、ピックアップトラックの需要が非常に高い地域です。また、タイはトヨタにとって重要な生産拠点でもあり、長年にわたってハイラックスの主力工場が稼働しています。
さらに、トヨタの会長である豊田章男氏が「タイは第二の故郷」と語るほど、トヨタとタイのつながりは強固です。経済・文化の両面で深い絆を持つこの国で新型を初公開することは、トヨタのグローバル戦略を象徴する出来事とも言えます。
2. 日本発売はいつ?気になるスケジュール

出典:TOYOTA
2-1. 日本発売は2026年年央予定
新型ハイラックスの日本国内での販売開始は、2026年の中頃が予定されています。具体的な月はまだ発表されていませんが、2026年の前半から夏前後にかけてディーゼルモデルの投入が計画されています。
現在、日本で販売されているハイラックスもディーゼルエンジンを搭載しており、引き続きその流れを継承する形での販売となる見込みです。長年にわたりファンに支持されてきたディーゼルならではのパワーと燃費性能に、最新のテクノロジーが組み合わさることで、より魅力的なモデルになることが期待されています。
2-2. 日本仕様はディーゼルモデルを展開予定
日本市場で導入されるのは、これまでの流れを踏襲し、ディーゼルモデルとなる予定です。この理由には、日本国内での軽油燃料インフラが整っている点や、SUV・トラックに対する実用性志向の高さが挙げられます。
新型ハイラックスにおいても、信頼性の高いディーゼルエンジンに加え、環境対策技術の進化が期待されており、排出ガス規制や燃費性能もクリアした上での導入が計画されているようです。
日本では近年、商用車だけでなくレジャー用途としてハイラックスを選ぶユーザーも増えており、そうしたニーズにもマッチする仕様になることが予想されます。
2-3. 欧州やオセアニア向けにはFCEVモデルも視野に
トヨタはグローバル展開を視野に入れ、新型ハイラックスのFCEV(燃料電池車)モデルの開発にも取り組んでいます。FCEVは水素を燃料とし、走行中にCO₂を排出しないクリーンなパワートレーンとして注目されています。
このFCEVモデルは、2028年以降に欧州やオセアニアでの投入が予定されており、環境規制が厳しい地域に向けた戦略的な動きといえるでしょう。日本市場では現時点で導入の予定はありませんが、今後の動向に注目が集まっています。
3. 価格はいくら?想定される新型ハイラックスの値段帯

出典:TOYOTA
3-1. 現行モデルと比較した予想価格
現在販売されているハイラックスの価格帯は、おおよそ390万円~450万円程度となっています。新型モデルに関しては、新たなパワートレーンや安全装備の強化、車体構造の刷新が行われていることから、価格は若干上昇する可能性が高いです。
予想される価格帯としては、ディーゼルモデルで400万円台後半〜500万円前後が目安になると考えられます。装備のグレードや駆動方式(2WD/4WD)によっても差が出るため、複数のバリエーションが展開されるでしょう。
3-2. EV・FCEV・ディーゼルで価格はどう変わる?
パワートレーンによって価格は大きく異なる見通しです。ディーゼルモデルはコスト面で最も手頃な価格帯となり、EV(電気自動車)モデルはバッテリーやモーター技術の影響で、若干割高になる傾向が見込まれます。
FCEVに関しては、水素タンクや燃料電池システムの高コストが価格に反映されるため、他のパワートレーンよりも高価になる可能性があります。欧州市場でFCEVが導入された際の価格は、同クラスEVの上位モデルと同等、もしくはそれ以上になると予想されます。
3-3. 補助金や税制優遇の可能性も解説
EVやFCEVなどの電動車両に関しては、日本国内でもさまざまな補助金や税制優遇措置が適用される可能性があります。たとえば、クリーンエネルギー車の導入促進補助金や、自動車重量税・取得税の免除などが該当するケースもあります。
こうした支援制度を活用することで、初期費用の負担を軽減しつつ、環境にも優しいカーライフを実現できるのは大きな魅力です。新型ハイラックスにおいても、導入時の政府支援策の有無によって、購入を後押しされるユーザーも少なくないでしょう。
4. どこが変わった?新型ハイラックスの主な変更点

出典:TOYOTA
4-1. 「マルチパスウェイ戦略」による多様なパワートレーン
新型ハイラックスでは、トヨタが推進する「マルチパスウェイ戦略」がいよいよ本格展開されます。この戦略は、世界各国のエネルギー事情やユーザーの使い方に応じて、複数のパワートレーン(動力源)を同時に展開するという方針です。
具体的には、ディーゼルエンジンをはじめ、バッテリーEV(BEV)、そして将来的には水素を活用するFCEV(燃料電池車)も視野に入れた多様化が図られています。これは単なる環境配慮だけでなく、実用性や長距離走行への対応、悪路走破性なども考慮された結果です。
ユーザーにとっては、自身の使用環境に合わせて最適なパワートレーンを選べるメリットがあり、「環境性能」と「使いやすさ」を両立させた次世代の選択肢として注目を集めています。
4-2. 航続距離300km超!EVモデルの性能詳細
新型ハイラックスのEVモデルには、総電力量59.2kWhのリチウムイオンバッテリーが搭載されています。このバッテリーは車体のフレーム構造を活かして床下に配置されており、重心を下げることで安定した走行性能にも貢献しています。
航続距離は300km以上を実現しており、都市部での使用はもちろん、週末のアウトドアや中距離の移動にも十分対応できる実力を備えています。充電効率にも配慮されており、日常使いのストレスを感じさせない設計が魅力です。
また、環境性能の高さに加え、走行時の静粛性や加速性能もEVならでは。ピックアップでありながら滑らかなドライブフィールが味わえる点も、大きな進化ポイントといえるでしょう。
4-3. eAxle採用で悪路走破性も強化
EVモデルの駆動システムには、効率的なパワートレイン設計を実現する「eAxle(イーアクスル)」が採用されています。これは電動モーター・インバーター・ギアボックスを一体化した構造で、軽量かつ高効率な駆動を可能にするユニットです。
eAxleの導入により、四輪駆動(4WD)システムとの組み合わせが最適化され、従来モデルよりもさらに優れたトラクション性能を実現。これにより、砂利道や雪道、ぬかるんだ地形などでも安定した走破性を発揮することができます。
さらに、モーター制御による緻密なトルク配分が可能なため、低速時の細やかな挙動コントロールが求められるオフロード走行にも対応。見た目以上に高性能な「本格派ピックアップ」として、信頼できる相棒になりそうです。
4-4. フレーム設計・重量配分・サスペンションの進化
新型ハイラックスでは、ボディ構造やシャシー設計も見直され、より高度なバランス性能を追求しています。特に、フレームの剛性向上と軽量化が同時に図られており、積載性能や走行安定性の向上にもつながっています。
バッテリーを床下に配置することで重心が下がり、前後左右の重量配分が最適化されました。その結果、高速道路でも安定した走りが可能になり、カーブでのふらつきも軽減されているとされています。
さらに、サスペンションは悪路走破性と快適性の両立を目指したセッティングになっており、オンロードでもオフロードでも心地よい乗り味が期待できます。見た目はタフ、でも乗り心地はしなやかという、まさに次世代の走りを体感できる1台です。
5. 内装はどう変わる?新型ハイラックスのインテリア
5-1. 新世代らしい高級感と先進装備
新型ハイラックスの内装には、これまでの商用車的な質実剛健さに加え、乗用車的な快適性と高級感がプラスされています。シート素材には質感の高いファブリックや合成皮革が使われ、長時間の運転でも快適な座り心地が確保されています。
インパネ周りには大型ディスプレイを採用し、最新のコネクティビティ機能に対応。スマートフォン連携、ナビゲーション、運転支援系の情報表示もわかりやすく、操作性にも優れた設計となっています。
加えて、運転席と助手席の空間設計には余裕があり、体格差のあるドライバーでも快適にドライブできるよう配慮されているのも好印象です。
5-2. 商用車からレジャー向けへ進化する室内空間
新型ハイラックスの室内は、単なる“働く車”から、日常とアウトドアをシームレスにつなぐ“ライフスタイル車”へと進化しています。リアシートの居住性も改善され、後部座席でもリラックスできる空間が確保されています。
特に注目されているのが、収納スペースの豊富さです。日常使いで重宝する小物入れから、アウトドアギアをしっかり収められる大型収納まで、用途に合わせた設計が随所に盛り込まれています。
このような工夫により、ビジネスユースからファミリーレジャー、そして災害時の移動手段としても活躍できる“マルチユース”なピックアップとしての魅力が一層強まっています。
5-3. EVモデルの内装設計の特徴とは?
EVモデルにおいては、エンジンやトランスミッションの不要な構造を活かし、より自由度の高いレイアウトが採用されています。センタートンネルの張り出しが少なく、フラットなフロア構造となっているため、足元の広さや乗降性が向上しています。
また、EV特有の静粛性を活かして、室内の快適性も大幅にアップ。ロードノイズやエンジン音が少ないぶん、オーディオの音質や車内会話のしやすさといった、ドライバーと乗員の快適性に直結する要素が高まっています。
未来的なデジタルメータークラスターやタッチパネルによる操作も、EVモデルならではの特徴で、乗り込んだ瞬間に“次世代感”を実感できる内装に仕上がっています。
6. なぜ今、多様化?トヨタの戦略とハイラックスの位置づけ
6-1. マルチパスウェイ戦略とは?
マルチパスウェイ戦略とは、トヨタが掲げる「カーボンニュートラル社会の実現」に向けた複線的な取り組みです。全ての地域が同じスピードでEV化できるわけではないという現実を踏まえ、ディーゼル・EV・FCEVといった複数の技術を並行して開発・提供していく方針です。
この戦略により、どの国・地域でもエネルギー事情やインフラに合った最適な車を選べるようになり、多様なライフスタイルと環境目標の両立が目指されます。ハイラックスはその先駆けとなるグローバルモデルとして、新たな役割を担っているのです。
6-2. 地域ごとのニーズに応えるグローバル展開
トヨタは、車両のグローバル展開において「一律で同じ仕様を提供する」のではなく、各市場ごとの特性に応じてパワートレーンや装備を柔軟に変える戦略を採っています。
たとえば、タイなどアジア地域ではディーゼルモデルの需要が根強く、日本もその流れに乗っています。一方で、欧州やオセアニアではFCEVのようなゼロエミッション車への関心が高く、それに応じたモデルの投入を計画しています。
このように、新型ハイラックスは単なる1車種にとどまらず、トヨタの多様化戦略の象徴的な存在となりつつあります。
6-3. 豊田章男会長が語る「タイとの絆」
今回の新型ハイラックスの世界初公開がタイで行われた背景には、トヨタとタイの深い関係があります。トヨタの豊田章男会長は、「タイは第二の故郷」と明言しており、同国との長年にわたる経済的・文化的な交流を非常に大切にしてきました。
ハイラックスは、タイ国内で“国民車”と呼ばれるほど親しまれており、トヨタの現地生産拠点としても大きな役割を担っています。今回の発表は、単なる新車の紹介ではなく、両国の信頼関係を象徴する重要なメッセージでもあったのです。
こうした背景があるからこそ、新型ハイラックスには“信頼される車”としての伝統と、“未来を切り開く車”としての革新性が共存しているのです。
おすすめ記事