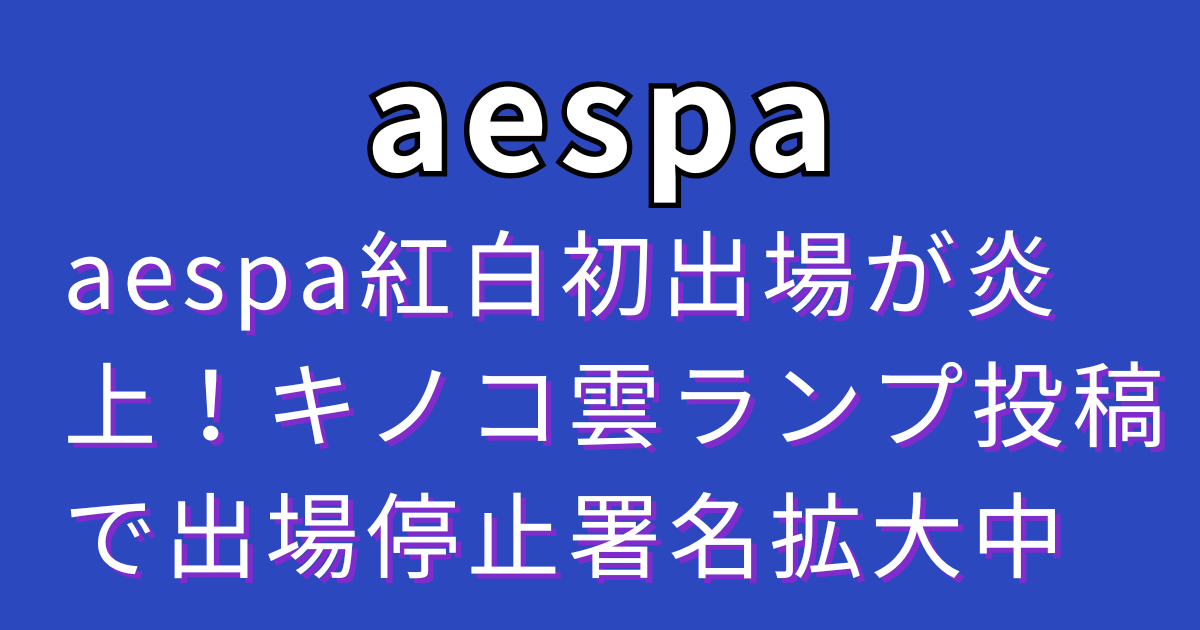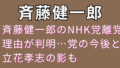K-POPガールズグループaespaの紅白初出場が決定した直後、SNS上では思わぬ騒動が巻き起こりました。発端は、メンバー・ニンニンが過去に投稿した「キノコ雲型ランプ」の写真──この投稿が原爆を想起させるとして再炎上し、紅白出場停止を求める署名運動にまで発展しています。タイミングは戦後80年、司会者やトリ候補も被爆地出身者が揃う年ということで、批判の声は一層強まりました。
この記事では、aespa炎上の背景と経緯、投稿に対する賛否、BTSとの比較、NHKや事務所の対応、そしてSNS時代における表現のリスクまでを多角的に解説します。
紅白という国民的番組で、なぜ今この問題が注目されているのか──その本質に迫ります。
1. aespa紅白初出場決定と即炎上の背景
1-1. 2025年紅白の注目ポイントとaespaの選出理由
2025年11月14日、NHKは第76回「NHK紅白歌合戦」の出場者を発表しました。注目のラインナップの中でも、特に話題となったのが、韓国の4人組ガールズグループ・aespa(エスパ)の紅白初出場です。デビューから瞬く間に世界的人気を獲得し、日本でも東京ドーム公演を成功させるなど、その勢いはとどまるところを知りません。
今回の出場は、aespaが2026年に予定している日本大規模ツアーの布石とも言われており、日本市場をさらに重視する姿勢がうかがえます。また、K-POP枠としての代表的存在であり、若年層の視聴率を意識したNHKの戦略とも考えられます。
ところが、出場発表の直後からSNSでは、aespaの紅白出演をめぐって賛否が渦巻く事態へと発展しました。特にメンバー・ニンニン(NINGNING)の過去投稿に注目が集まり、炎上騒動が急拡大していきました。
1-2. 「#aespa原爆ランプ」炎上の発端とは?
炎上のきっかけとなったのは、aespaの中国出身メンバー・ニンニンが2022年にファン向けアプリ「Bubble」に投稿した写真です。そこには、キノコ雲の形を模したインテリアランプが映っており、「可愛いライトを買ったよ〜どう?」という無邪気なコメントが添えられていました。
この投稿が、原爆を想起させるものだとして、日本の一部ネットユーザーの間で問題視されることになります。当初は一部で指摘される程度でしたが、紅白という国民的番組への出演が決まったことを契機に、「#aespa原爆ランプ」「#aespa紅白出場取り消し」といったハッシュタグが急浮上。炎上の火が再び燃え上がる結果となりました。
批判の声は、「被爆国・日本の国民的番組に出る資格があるのか」「公共放送として適切なのか」といった厳しいものが多く、出演自体を見直すべきという意見も少なくありませんでした。
2. ニンニンの過去投稿と「原爆ランプ」問題の詳細
2-1. 問題視された投稿内容とランプのデザイン
ニンニンが投稿した写真に写っていたのは、「キノコ雲型LEDランプ」と呼ばれるインテリア雑貨でした。この商品は海外のECサイトなどでも一般的に販売されているもので、戦争や歴史的背景に直接言及するような意図は見られません。
ランプ自体は、爆発直後に広がるキノコ雲の形を模したデザインで、内部にはオレンジ色のLEDライトが仕込まれており、点灯すると雲が淡く光ります。ニンニンはこのランプを「可愛い」として紹介しましたが、その見た目が「原爆のキノコ雲」を連想させると受け取られたことが、今回の炎上の根底にあります。
2-2. SNS上の初期反応と炎上までの経緯
投稿されたのは2022年であり、当時も一部のファンから「原爆を想起させるのでは?」という懸念が出ていたものの、大規模な炎上には至りませんでした。
しかし2025年の紅白出演が発表された瞬間、SNS上ではこの古い投稿が再び掘り返され、怒りの声とともに拡散されました。特にX(旧Twitter)上では、批判的なツイートが数万件規模でリツイートされ、「aespaの出場取り消しを求めるオンライン署名」まで立ち上がる騒ぎに発展しました。
炎上のスピードは非常に速く、「日本人の感情を軽視している」「被爆地出身の司会者やトリ候補がいる中で不適切」といった意見が中心となり、ネット上で大きな論争となっています。
2-3. 被爆国・日本での「キノコ雲」へのセンシティビティ
日本において「キノコ雲」は、広島と長崎に投下された原子爆弾の象徴として、非常に重い意味を持つ存在です。そのため、たとえ悪意がなかったとしても、その形状を模したものを「可愛い」と表現することは、多くの人々にとって不適切に映ります。
特に高齢者や戦争体験者、その家族にとっては非常に敏感な話題であり、戦後80年という節目を迎える今年は、例年以上に社会的な注目が集まっています。
ニンニンの投稿が「可愛いライト」として紹介されたことに対し、「無知」「無神経」「歴史認識に欠ける」といった批判が出ているのは、こうした背景が影響しています。
3. 騒動再燃の理由と“2025年”という特異性
3-1. 戦後80年という節目
2025年は、第二次世界大戦終結から80年という節目の年にあたります。国内では戦争と平和について改めて考える機会が増えており、学校やメディアでも戦後の歩みや被爆の歴史を振り返る特集が多く組まれています。
そうした中で、キノコ雲を想起させる投稿を過去に行った海外アーティストが、日本の国民的番組に出演することに対し、「タイミングが悪すぎる」「配慮が欠けている」との声が噴出しています。
一見、過去の小さな出来事でも、特別な年には社会的に大きく取り上げられるリスクがあるのです。
3-2. 司会者・トリ候補に「被爆地出身者」が揃う異例の構成
さらに2025年の紅白では、司会者として広島県出身の有吉弘行さん、そして長崎県出身の綾瀬はるかさんが起用され、トリ候補にも長崎出身の福山雅治さんやMISIAさんが有力視されています。
これにより「被爆地にゆかりのある出演者が揃う年に、過去に原爆を連想させる投稿をしたグループを出演させるのは適切か?」という疑問が強まっています。
つまり、紅白という舞台が偶然にも「被爆の記憶」と密接に結びつく構成となっていたことが、炎上の火に油を注ぐ形になったとも言えるでしょう。
3-3. 過去の投稿が“今”影響するSNS時代のリスク
ニンニンの投稿は3年前のものであり、当時はさほど大きな話題になりませんでした。しかしSNSの特性上、過去の発言や投稿がスクリーンショットで保存・拡散され、数年後に突然問題視されることは珍しくありません。
このような時代では、アーティストや有名人ほど、何気ない投稿にも高いリスク管理が求められます。炎上しやすい社会の中で、投稿ひとつが未来のキャリアや活動に影響を及ぼす可能性があることを、私たちは改めて考える必要があるでしょう。
4. 出場反対の署名運動と世論の二極化
4-1. 「aespaの紅白出場停止を求める署名」がXで拡散
aespaの紅白初出場が発表された直後から、SNSではある一つの投稿が大きな注目を集めました。それは「aespaの紅白出場停止を求めます」と書かれたポストで、X(旧Twitter)にて署名活動への参加を呼びかけるものでした。該当ポストは瞬く間に拡散され、数十万回以上の閲覧数を記録。リツイートやコメントも殺到し、紅白出演に反対する声が一気に可視化される事態となりました。
投稿では、オンライン署名サイトのリンクも添えられており、そこには「原爆を想起させる投稿をしたアーティストを、国民的音楽番組に出演させることは容認できない」といった主張が記されています。11月17日時点で、この署名には多くの賛同者が集まっており、短期間での反応の大きさが世論の敏感さを物語っています。
このようなオンライン署名活動が行われること自体、紅白歌合戦という番組が持つ社会的影響力の大きさを改めて示していると言えるでしょう。
4-2. 批判側の主張:「日本人の感情を無視」「公共放送として不適切」
aespaの紅白出場に反対する人々からは、主に次のような意見があがっています。
「被爆地・広島や長崎の出身者が関わる今年の紅白に、原爆を連想させる投稿をした人物が出演するのは無神経すぎる」
「日本の公共放送であるNHKが、国民の心情に配慮せず選出するのは問題ではないか」
「過去の投稿だからといって、被害者感情を軽視していい理由にはならない」
こうした意見は、特に高齢層や歴史認識に敏感な層を中心に強い支持を集めています。また、紅白の視聴者層が広範であることから、「子どもも観る番組でこのような問題が放置されて良いのか」といった道徳的観点からの疑問も出ています。
加えて、「紅白は日本文化を象徴する番組であり、出演者の選定には相応の社会的責任が伴うべき」という主張も見られ、ただの炎上では片付けられない空気が広がっています。
4-3. 擁護派の声:「悪意なし」「意図的ではない」「差別的反応こそ問題」
一方、aespaの出演に理解を示す意見も数多く存在しています。主な擁護の論点は以下の通りです。
「ニンニンの投稿は単なるインテリア紹介であり、原爆を揶揄する意図はなかったはず」
「3年前の投稿を今になって掘り返して騒ぐのはフェアではない」
「文化の違いを考慮せずに過剰に反応するのは、むしろ差別的ではないか」
aespaのファンのみならず、K-POP文化全体を支持する層からは「感情論だけで出場停止を求めるのは言いがかりに近い」といった意見もあり、批判派に対して冷静な議論を呼びかける声も多く見られます。
さらに、アーティスト個人に対する誹謗中傷や人種差別的な発言に対しても懸念が広がっており、「議論は必要だが、感情的な排除は慎むべき」というスタンスを取る人も増えています。
5. BTS原爆Tシャツ問題との比較
5-1. 両者の経緯・背景・投稿内容の違いと共通点
aespaの騒動は、2018年に話題となった「BTS原爆Tシャツ問題」と比較されることが多いです。BTSのメンバー・ジミンが着用したTシャツには、原爆のキノコ雲と「韓国独立」の文字がプリントされており、日本の降伏を祝う意図が明確に表現されていました。
それに対して今回のaespa・ニンニンの投稿には、政治的メッセージや歴史的文脈は存在せず、あくまで可愛い雑貨として紹介されたものでした。ランプは市販されている一般的な商品であり、投稿文にも特別な意図は見受けられません。
共通しているのは、いずれも「原爆を想起させる表現」が問題視された点と、それが日本のメディア出演に影響を及ぼしたことです。しかしその背景や文脈、炎上の規模、社会的反応には明確な違いが存在します。
5-2. メディア対応の差と「学習効果」の有無
BTSの場合は、Tシャツ騒動を受けて日本の音楽番組への出演がキャンセルされ、事務所側からも公式の釈明が行われました。批判と擁護の意見が真っ向からぶつかり合い、最終的には「日韓間の歴史認識の違い」にまで議論が拡大しました。
一方、今回のaespaに関しては、2025年11月中旬時点で事務所・SMエンターテインメントもNHKも沈黙を貫いており、公式な対応やコメントは一切出ていません。炎上の温度感が高まる中で、明確な対応をしないことが逆に批判を加速させている側面もあります。
また、BTS騒動を経た今だからこそ、芸能界全体に「過去の事例から何を学ぶか」という問いが突きつけられているとも言えるでしょう。ファンや関係者にとっても、今回の件は「表現の自由」と「歴史認識の尊重」のバランスを再確認する重要な機会となっています。
6. 事務所・NHKの対応と出場取り消しの可能性
6-1. SMエンターテインメント・NHKの「沈黙戦略」
aespaの所属事務所であるSMエンターテインメントは、これまでにも複数の炎上騒動に直面してきましたが、今回の件についても現段階では沈黙を貫いています。ニンニン本人からの発言もなく、ファン向けのアプリ「Bubble」やSNSも通常通りの投稿が続けられています。
一方で、紅白を主催するNHKもまた「出演者の変更は予定していない」との姿勢を崩しておらず、騒動に対して表立ったコメントを控えている状況です。過去の類似案件では、メディアが出演取り消しを決断した例もありましたが、今回は異なる対応を選択しているようです。
この「静観」の姿勢が今後どのような影響を及ぼすのか、注目が集まっています。
6-2. 現実的に出場中止の可能性はあるのか?
現時点では、aespaの紅白出場が取り消される可能性は低いと見られています。その理由としては、以下のような点が挙げられます。
・投稿は3年前のもので、法的・倫理的に直接的な違反がない
・明確な謝罪や釈明がなされていないため、世論が割れている段階
・aespaの人気と話題性が高く、視聴率への貢献が見込まれている
・NHKが公共放送として安易な中止判断を避ける傾向にある
ただし、炎上がさらに拡大し、国会や自治体など公的機関からの意見表明が出てくるような事態になれば、対応が変わる可能性もゼロではありません。
6-3. 謝罪・釈明が世論を変える可能性
過去の類似騒動から見ても、アーティスト本人や事務所からの誠意ある謝罪や説明が、世論を大きく動かすことは珍しくありません。特に、投稿に明確な悪意がなかったことが丁寧に説明され、被爆国・日本への敬意や理解が示されれば、一部の批判も落ち着く可能性があります。
また、紅白という場を逆に「文化理解を深める機会」として活用できれば、騒動を乗り越えるきっかけになるかもしれません。今後、どのようなタイミングで何を語るかが、aespaと所属事務所にとって非常に重要な分岐点になると言えるでしょう。
7. 国際アーティストに求められる配慮と教訓
7-1. 歴史認識の違いと表現の境界線
国際的なアーティストが活動するうえで、避けて通れないのが「歴史認識の違い」による摩擦です。今回のaespa・ニンニンによるキノコ雲型ランプの投稿が日本で問題視された背景には、原爆という非常に繊細な歴史的事実が深く関係しています。
日本では広島・長崎の被爆体験が今も語り継がれており、原爆の象徴とされる「キノコ雲」は決して軽々しく扱われるべき対象ではありません。一方で、中国や韓国など他国においては、原爆が「戦争終結の引き金」や「歴史的な出来事の一部」として捉えられるケースもあり、そこには文化や教育の差が存在します。
ニンニンの投稿自体には明確な政治的メッセージや敵意はなく、単なるインテリア紹介であった可能性が高いと考えられますが、結果的にそれが「被爆国・日本」の視点から見て重大な無神経と捉えられてしまったのです。
表現は自由である一方で、それが国や文化を超えたときにどう受け取られるかという配慮もまた必要不可欠です。特に、数千万人規模のフォロワーを持つようなアーティストの場合、言葉やビジュアルの選び方ひとつが思わぬ社会問題へと発展してしまうことがあります。
「自国では問題視されないことでも、他国では大きな傷をえぐる表現になり得る」──この感覚を持ち続けることが、グローバルで活動するアーティストには強く求められています。
7-2. SNS時代のグローバルアーティストが持つべき責任
SNSの普及により、アーティストとファンの距離はかつてないほど近くなりました。写真一枚、短いメッセージ一つが、リアルタイムで世界中に届き、あっという間に拡散される時代です。
そんな時代において、国際的に活動するアーティストは、自身の発信が与える影響を冷静に捉える力が求められます。今回のように、過去の投稿が数年後に再燃するというケースも多く、投稿した瞬間だけでなく「いつどんな文脈で見られるか」という未来の視点も必要です。
また、投稿が炎上した際に重要となるのは、その後の対応です。沈黙を貫くか、釈明するか、謝罪を表明するか──その選択ひとつで、アーティストの信頼度や社会的な評価は大きく変わってきます。
特にaespaのように、韓国・日本・中国などアジア各国をまたにかけて活動するグループにとっては、各国の文化や感情に対する深い理解が、キャリアの安定や拡大に大きく影響します。
今後、同様の問題が他のアーティストにも起こる可能性がある中で、ニンニンの件が「国際アーティストにとっての教訓」として広く認識されることが求められています。
8. まとめ|紅白出演は“文化摩擦”と向き合う場にもなる
8-1. aespa問題が投げかける「表現と配慮」の問い
aespaニンニンによる過去の投稿が、紅白出場という晴れ舞台の直前に問題視された今回の一件。投稿当時は大きな注目を集めなかったにもかかわらず、数年後に再び掘り返され、社会的な論争へと発展しました。
この騒動が示しているのは、「表現の自由」と「配慮すべき歴史・文化」とのバランスの難しさです。何をもって“悪意がない”と判断するのか、どこまでが許容されるのか──これらの境界線は時代や国によっても大きく異なります。
また、SNSが普及した現代では、情報が瞬時に国境を越え、多様な価値観の中で受け止められることを前提とした言動が求められています。
aespaの紅白出演をめぐる騒動は、単なる「炎上事件」ではなく、国際的な文化交流における複雑な課題を浮き彫りにしたとも言えるでしょう。
8-2. 年末の舞台で“対話のきっかけ”となる可能性も
今回の紅白歌合戦は、「戦後80年」という特別な節目にあたります。有吉弘行さんや綾瀬はるかさんといった、被爆地出身の司会者が起用される中で、aespaが出演することは賛否両論を呼んでいます。
しかし一方で、このようなタイミングだからこそ、国境を越えた理解や対話を進める“きっかけ”になる可能性もあります。仮にaespaや事務所がこの問題に対して何らかの説明や誠意を見せた場合、それは文化摩擦を超えた「新たな橋渡し」の象徴にもなり得ます。
音楽という共通言語を通じて、歴史や文化の違いを乗り越えていくことができるのか──紅白という大舞台が、国際的な対話の場となるかどうかは、出演者と放送側の今後の姿勢にかかっていると言えるでしょう。
おすすめ記事
川村壱馬はなぜ活動休止?理由・復帰の見通しとTHE RAMPAGEの対応